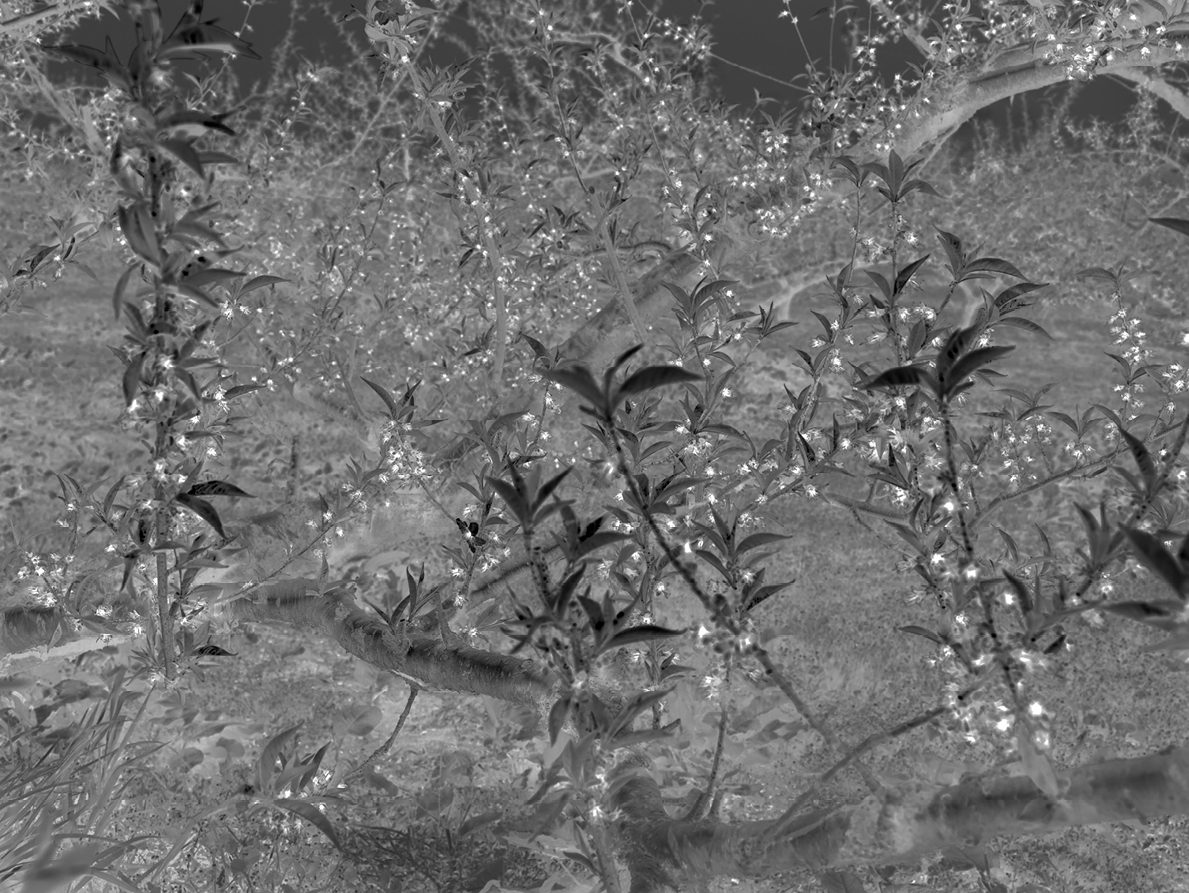2万発もの花火が夏の闇を吹き飛ばす隅田川の花火大会。川岸には数十万の群衆が夜空を仰ぎ見ながら、今か今かとその瞬間を心待ちしている。
そんな光景に接するたびに思い浮かべるのは、木村伊兵衛の「川開き 蔵前」(1953年)という作品だ。夏の夜空に炸裂しては瞬いて消えるつかの間、今日よりもさぞ濃く深かったであろうあのころの闇の中で、花火がくっきりと際立っている。輝く光そのものとそのシルエットである漆黒の闇の輝きがそこにはある。60年前の出来事が幻のようだ。
Essay
-
「木村伊兵衛 今日的写真の先駆」2014/5/7 朝日新聞
-
Varzea/バルセア・・・消えゆく土地
Site Soleil / Haiti , 2009
南太平洋のタヒチとよく間違えられるが、そうではない。
ハイチだ。
カリブ海の島国でキューバやジャマイカの近くにあるが、
まったく美しい国とは言えない。
褒めようがないのだ。
着いたその瞬間、帰りたくなる。
1%の富裕層が山の頂きに住み、用事でもないかぎり彼らは山を下りようとはしない。 -
ガラスの船
雨は止むどころか激しさを増して降りつづいていた。
車内を煌々と照らす先に眼をやれば、雨足の向こうに明かりが滲んでいた。眩いネオンが色とりどりに点いては消え、消えては色を変えて雨の夜を侵していた。前方に3台ほどのワゴン車やトラックが並んでいた。売店に違いない。僕はスピードを落として、ずっと走って来た追い越し車線から走行車線に入り、さらにゆっくりと路肩の砂利道に車を寄せようとしたとき、BMWが割り込んできた。
-
「歩く眼」・・・walking eyes
路地に雨水があふれて、小川のようになっていました。
ひび割れた路面に染み入る間もなく、生ぬるい水は「南海」から「子どじ」の前を過ぎて、花園神社のほうへ向かって流れていました。その夜も、深瀬さんはいつものように「サーヤ」を出て、雨の中を「南海」に向かったに違いありません。流れに逆らいながら、川でも溯るように歩いて行ったのです。1週間ぶりの、深瀬さんには久しぶりのゴールデン街でした。 -
セシウム
東北自動車道を時速140kmで北上して行くと、1時間ほどで風景が一変する。
大気そのものが違って感じられ、宇都宮を過ぎた辺りにさしかかると僕は決まって、東京からの冷房で冷えきった車内の空気を追い出すように車の窓を全開にする。
すると、湿った生暖かい空気が一気に吹き込み、乾いた肌をべとつかせた。3月に父が亡くなるまでのひと月とそれからの四十九日までの間、毎週のように僕は実家のある福島に通っていた。
冬から春へ、そして夏へと移り行く季節を疾走する車から眺めつづけた。 -
追悼 深瀬昌久
高台にある施設には、いつも午後の陽が溢れていた。木々が覆いかぶさる緑地が、眼下に細く長く伸びている。僕は、深瀬さんを見舞うのは、晴れた日の午後1時ごろと決めていた。車いすでその公園を散策することぐらいしか僕にできることがない。深瀬さんが倒れて3年間くらいは自分の名前を書いたり、僕のことを認識したりできていた。時には、こっそり煙草を吸わせては様子を観察し、いったい深瀬さんは今どこにいるのか推測したものだ。しかし、いつの間にか深瀬さんはただ窓を眺めているばかりとなっていた。
ある午後、久しぶりに訪ねた時に、ふとベッドの枕元に置いてあるノートをめくってみた。見舞客が名前を書いたりするメモ用のノートだ
「狂、狂、狂、狂、狂、狂、狂、狂、狂、狂、狂、・・・・・・」 -
二つの故郷
タイの特集なのに、ここには場違いの写真が並んでいる。
タイの東北地方の町、ウドーンタニ市近郊の田園風景と福島盆地を流れる阿武隈川、
スコールで濡れる南国と雪降る北国、そして、カラーとモノクロームの白と黒、一見して何の関係もないかのように思われる。
しかし、僕にとってはこの2枚の写真は、ネガとポジの関係で、重ね合わせれば、
印刷の赤版と青版のようにピタリと重なって1枚になる。また、目を細めて1点を見つめれば、それぞれのイメージが分かれて2つになり、遠い記憶も分裂してそれぞれの時間、それぞれの居場所へと、いとも簡単に落ちてゆく。
僕には2つの名前がある。
<瀬戸トオイ>と<瀬戸正人>タイの名前そのままの<トオイ>は本名で、<正人>は呼び名としての日本名、父の故郷の福島に移り住んだときに名づけられた。 -
森山大道 大阪国立美術館
神田川を見下ろしながら、ふたり電車を待つ。
深い川床を流れる水面は暗く、その水音も聴こえては来なかったが、お茶の水駅のホームには、眼下からわき上がって来た春の水の匂いが、辺りに溢れていたのを忘れられない。午後9時、写真学校のゼミの帰り、横浜から学校に通っていた僕は、逗子に帰える森山大道さんといつも一緒にこのお茶の水駅で電車を待ち、東京駅で横須賀線に乗り換えた。同乗した30分の間、ボックス席で向かい合わせに座り、僕は目の前の写真家を不思議そうに眺めていた。沿線の桜が、電車内の灯りを受けながら夜の暗がりに浮かんでは消えて、また浮かびあがっていた。写真家とはいったい何者なのか?これから写真に飛び込もうとする僕にとって、言いようのない不安ばかりが募ったものだ。 -
M型写真ヴィールス
フットスイッチを踏むと印画紙に画像が投影された。画面いっぱいに、何かの花が反転されて映し出されている。白い花だ。白いはずの花びらが、紙のうえでくっきりとした影となって黒々としている。そして、その花影から光が光そのものとして零れていた。
20年ほど前の夏のことだ。
僕の仕事場の、バスルームを改良した狭い暗室の暗がりでふたり並んで、僕が印画紙に露光し、それを森山さんが現像していた。ふつうは逆だ。露光のほうが大事だから、森山さん本人が露光をして、アシストする者が現像をするものだ。どうしてそうだったのか思い出せないが、確かに僕は森山さんのネガをセットして露光をしていた。
-
森山大道全作品集 1
本の重さを量ろうなどと思ってみたこともないが、あまりにも重いので体重計にのせてみた。2.9キログラムもあった。念のためにその本を抱えてのったら、自分の体重が3キロ増え、体脂肪もぐんと増えて、何だか森山さんを抱えている気になった。動くたびに変動する数値を気にしながら、計りのうえで1973年のページをめくった。1964年のデビュー作からはじまる分厚い本の最後の章だ。写真学校に入学するために上京した、あのころに見たはずの写真を真っ先に確かめたかったのだ。「アサヒカメラ」に連載されていた、〈地上〉と題されている写真にはちがいなかったが、思っていた写真は見あたらない。おぼろげな目の記憶で、整然とならぶ写真とそのキャプションの文字を行ききしながら時代を溯ってゆくと、その直後に森山さんに出会うことになるぼくには、もうわからない領域になってゆく。折々に聴いていた写真のエピソードを思い返しても、知っている写真はわずか2、2割で、愕然とさせられる。
-
1999年の幸福論
なぜかあの時の光景が忘れられない。トヨタの大衆車「ファミリア」がゆるいカーブを曲がりながら、真新しい団地の丘をあがっていった。白い建物と芝生の陰影がくっきりとしていて、眩しい。辺りには 午前中のものと思われる清々しい空気がそこかしこに漂い、立ち並ぶ同じ形の建物の上空には雲ひとつない青い空が広がっていた。初夏だった気がする。街路樹がまだ植えられていないはずなのに、季節を感じさせる木々がどこにも見あたらないのに、なぜかそう思い込んでいる。
-
わが青春のヒーロー、力道山……1961年
そこかしこに堆肥の甘い匂いが漂い、見わたせば、盆地の中の、骨みたいに白く立ち並ぶ桑畑に囲まれていた。母も生まれ、僕も生まれたタイ国の片田舎町のウドーンタニから、父に連れられて福島県の農村に移り住んだのは8歳の時だった。そこは父の実家だった。昭和17年に出征して行った父が20年もの間、音信不通だったため死んだものと思い、次男の正次が継いだ農家でもあった。
1961年、僕はまだ〈トオイ〉と呼ばれていた。
ウドーンタニの写真館を整理して、3年したら母と弟と妹を連れて戻るからと言い残して父はタイに帰り、それからの3年間をこの村の桑畑に囲まれた藁葺き屋根で暮らすことになった。桑の葉を喰って透明になってゆく蚕のように、堆肥の匂いの中で、ラジオから流れ出る吉永小百合の歌声が涙で濡れるのを聴きながら、意味もわからずに口ずさんでいるうちに、僕は〈トオイ〉から〈正人〉になり、日本人になってゆくような気がしていた。兄貴分でどこへ行くにも一緒に連れて行ってくれた実さんが、1円玉を握って「見せてくないしょ」と言って立ち寄った村の地主の家で、はじめて見たテレビに力道山が縦横無尽に立ち回る姿があった。金髪を振り乱し、額に噛みつくなど思いもよらない事をするブラッシーは、獣であり敵そのものだった。血だらけになった力道山がふらつき、もしかしたら噛み殺されるのではないかとさえ思ったものだ。しかし、リキが力を振り絞って伝家の宝刀空手チョップを振り下ろせば金髪の獣も羊に見えて、一発一発、日々鍛えあげた肉体に力がみなぎり、見ているだけで勇気づけられたものだ。