東北自動車道を時速140kmで北上して行くと、1時間ほどで風景が一変する。
大気そのものが違って感じられ、宇都宮を過ぎた辺りにさしかかると僕は決まって、東京からの冷房で冷えきった車内の空気を追い出すように車の窓を全開にする。
すると、湿った生暖かい空気が一気に吹き込み、乾いた肌をべとつかせた。
3月に父が亡くなるまでのひと月とそれからの四十九日までの間、毎週のように僕は実家のある福島に通っていた。
冬から春へ、そして夏へと移り行く季節を疾走する車から眺めつづけた。
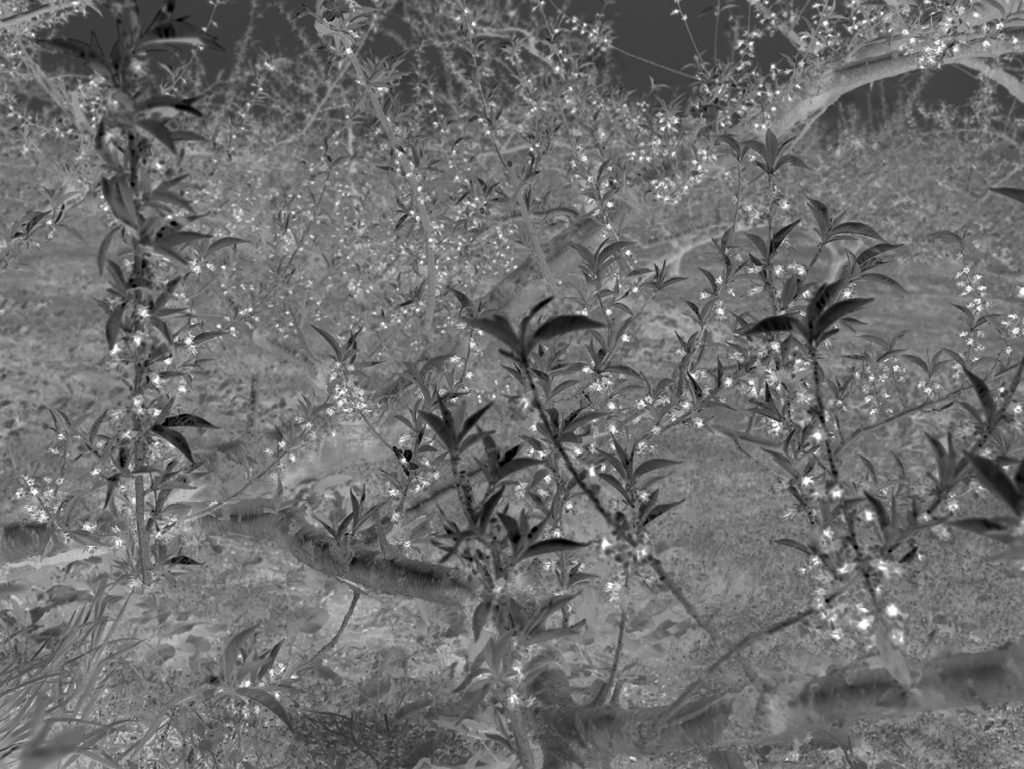
ある時、太平洋沿岸を北上する台風9号に追われて、走っていたことに気がついた。熱帯から運ばれてきた南国の匂いなのか、それともそこここに生い茂る夏草の草いきれなのか、その密度ある夏の匂いに息をつまらせた。
遠くの山々の背景には夏の空と雲が湧き上がっている。そこに強い日差しが当たっているにもかかわらず、突如としてワイパーもきかないほどの豪雨の中に突入したり、数分もすればそれがまるでなかったかのように乾ききった路面に戻っている。
車は走りつづけている。
フロントガラス越しに青い稲が揺れていた。もくもくと湧き上がる真っ白な入道雲とそのはるか上空に一筋の飛行機雲がうっすらのびて散りかけているのが見え、同時にバックミラーを覗くと黒々した雨雲が遠ざかって、もう秋なのかまだ夏の盛りにいるのかわからなくなる。車内に吹き込み渦巻いている風さえ夏のものとも秋のものとも感じられ、季節の変わり目のまさに最前線にいる気がしたのだった。
東京では桜も散って初夏めいていたころには、那須の山裾に山桜がまるで「ここにいる」とでも言っているように、雑木林の薄緑色の若葉に囲まれ揺れていた。
見ようとすれば葉脈の一筋一筋が見える気さえした。その葉の色が透けるほどに薄く山をつつみ込み、その稜線が産毛に覆われたかのようにぼんやりとして、何十kmにもわたって春の景色が高速道路の両わきにつづいていたのだった。そして北上するにつれ、山並みは新緑の春から冬の終わりのまだ枯れたままの木立に変わり、季節がゆっくりと逆戻りする。
福島と東京の行き来を繰り返すうちに盆の入りになって、我が家にとってのはじめての初盆で亡き父を迎えた。仏壇の両側に竹を立て提灯を吊るした。昆布やトウモロコシ、麩などを枝に結わえつけ、床にカボチャやスイカ、ニンジン、ナス、キュウリなどの夏野菜を並べた。そして蓮の葉を広げると、母は寺の住職が言っていた「仏さまを迎えて、存分にご馳走してあげるのがお盆ですよ」という言葉を思い出したのか、炊き立てのご飯だけでいいのに、あれこれと父に食べさせたくて一度に何種類もの料理をのせていた。その日から3日間、朝、昼、晩と欠かさずあげなければならないのに、すでに山盛りになっていた。
夕方、提灯に火を灯すとほんとうに父が帰って来た気がしたのだった。通りに出ると小さな町の商店街に提灯がとぎれとぎれにも連なり、風に揺れていた。町のそこここで祭りの準備が始まっているらしい。ゴーストタウンのようになってしまった故郷の町も、この時だけは昔のような賑わいを取り戻したのか、浴衣を着た娘たちが夕闇を歩き、遠くに近くに笛や太鼓が響いていた。
僕は、もう何年もこの夏祭りにいなかったことに今さらながら気がついた。父を迎えた午後が夏の盛りなら、この夕暮れはもう秋だ。夏に打ち上げた花火が秋の夜空で炸裂しているような気もする。
送り盆の午後、習わしにしたがって最後のご馳走のうどんを箸でつまんで差し出すと、まるで父がすすっているかのように、そのうどんがするすると蓮の葉にすべり落ちた。セミが鳴き狂う真夏の昼と夕暮れからの秋の風が交互に入れ替わり、わずか3日間でその年の夏はどこかへ行ってしまった。
それからの10年間ほど、その福島には平和な日々がつづいていた。
台風も来ないし地震もない、本当に穏やかでいいところだと父が言っていたのを思い出しながら、僕はいつになく陰鬱な思いで車を走らせていた。東北自動車道は封鎖され、やむなく国道4号線を北上するほかなかった。国道も地震の影響で道が波打ち、うまく走れない。ラジオをつければ緊迫したアナウンサーの声が途切れることなく溢れてくる。
2011年、3月11日から10日目のことだ。
僕は、実家のある福島の中通りの町でガソリンを調達し、すぐに阿武隈山系の峰を越えて相馬の海に向かっていたのだった。
空は青空、静まり返った地平に風が吹き抜けてゆく。揺らすものでも探すかのように海からの風が頭上を舞い、吹き降ろす。津波で突き飛ばされ開け放されたままの窓をすり抜けて、風はすでに乾いてしまったカーテンを揺らしていた。窓という窓には、不思議にもカーテンだけが流されずにはためいているのだった。
そこかしこに漂う異臭を潮風がさらって行く。春めく空のどこかでヒバリの声が舞っていた。子どもの頃に河原でよく耳にしたあのか細い鳴き声を思い出すも、辺りにその姿は見あたらない。
僕は、広大な湖と見まがうような風景の中を走っていた。
自衛隊員が装甲車の影の地面に座り込んで昼食をとっていた。僕はその横を通り抜けて、ひび割れたアスファルトの路面を避けて車を止めた。湖の真ん中に立っているかのような場所で、辺りを呆然と眺めるほかなかった。そこは湖ではなく、水没した田畑や水田だったのだ。どうすればこんなにも潰れるのか、農機具や車などが鉄の塊となって散乱し、ほとんどがひっくり返ったまま水に沈んでいた。その水の中を、鉄棒を手にした10数名の自衛隊員が一列に並んで、黙々と遺体を捜索していた。
現場を見に来た老人がひとり立っていた。田植えを控えていた自分の水田を見下ろしながら、土地が3mほど陥没し土壌も流されて、舗装されたこの農道だけが土手のように残ったのだと言う。「むか~し、埋め立てて作った田んぼだべ~、昔さ返っただけだ~ぁ」と、目の前に立ち現れた子どもの頃の景色が懐かしいとでも言うように、流されずに残った海辺の松を指さすのだった。日に焼けたその老人の訛った言葉が、福島の大地に吸い込まれてゆくのが目に見える気がしたのだった。
その日、目にしたことは始まりに過ぎなかった。
その翌日から、僕は津波を止めた国道6号線を北上していた。道の左右にはまったく別の、違った風景が広がる。右手の海側に広がる被災地からの汚泥匂う風が車内に吹き込み、頬を撫でては山側の、津波を免れた家々の方へと抜けてゆく。
春はすぐそこにあった。
相馬→名取→気仙沼→陸前高田→石巻→女川→松島→塩竈→宮古→釜石→大船渡→南三陸……
北上すれば海は右手にあり、南下時には常に大海原は左側の眼下に広がっていた。
松の木がいたるところに根をおろし、山かげに溶け込んでは背後の海にその輪郭を際立たせていた。どの町も海に向かって開けた三角の狭い土地で、人々はいつも山を背負い海に向いて生きているのが手にとるようにわかる。
流す涙で割る酒は
だました男の味がする
あなたの影をひきずりながら
港、宮古 釜石 気仙沼
森進一の「港町ブルース」のこの一節に惹かれてひとり旅をしたのは、もう20数年も前のことだ。連なる港をめぐり、いつもこの歌を口ずさみながら写真を撮ったものだ。時に人目を忍んで海に向かってひとり絶唱すれど、寄せて来る波音にすぐにかき消された。もう、どの町のどこを探しても当時の面影はない。今、どこにでも破壊された生活の残骸が広がるばかりで、海辺から山裾まで泥の色ただ一色、流した涙を拭う気力さえないだろう。
南三陸町の、流されずに残った防波堤に階段があった。
がれきと泥水で淀み、見るも恐ろしい光景があるのではと、恐る恐る這い上がって入り江を覗き込んだ。すると、何もなかったかのように青いばかりの海が岸辺を浸し、陥没しかけた岸壁の淵でカモメが並んで羽を休めていた。入り江の海水が全部入れ替わったのだろうか。巨大な防波堤の外は、深海のような青さと静けさで不気味でさえあった。
ここでも風が行く先に迷い、賽の河原のようになってしまった風景の中で揺らすものを探していた。10mはあろう防波堤の高みからは、流されずに残った病院などの鉄筋コンクリートの建物の窓がくっきりと見渡せる。
そして、人のいないどの家の窓でも洗い立てのようなカーテンが、風に吸い出されてはためいていた。動くものは他に見あたらない。眩いほどに翻るレースカーテンの白さは、その奥の空洞のような暗がりをいっそう深く感じさせた。その暗がりに人の気配がする。竜宮への入り口でもあるかのように、こちらに向かって手招きしているようにも思える。
海も山も見渡せる防波堤から降りる時、ふと、えも言われぬ不安がよぎった。もしかしたら今、高みから地上に降りているのではなく、僕は海の底に降りているのではないかと、足がすくんだ。
そうだ、ここは海の底だったのだ。人はそれを忘れている。何万年か前、ここは紛れもなく海に沈んでいたはずだ。昔々、そこが海の底だったことを僕らに思い知らせるかのように、海は町を沈め、アンモナイトが眠る崖を這い上がっては人々を深い海底に連れ去ったのだった。